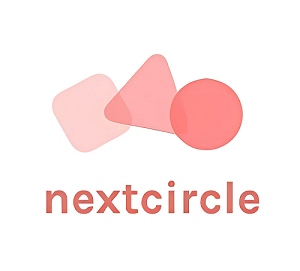緑色の正体
牡蠣の身の中に見える緑色の部分は、主に消化腺(中腸腺、いわゆるヘパトパンンクレアス)と呼ばれる器官に由来します。
この部位は牡蠣の「肝臓」と「膵臓」に相当する重要な消化器官で、餌として摂取した植物プランクトンや藻類の色素が蓄積するため、緑色や黄緑色に見えることがあります。
特に牡蠣が緑藻や藍藻などを多く含むプランクトンを食べている場合、その色素が消化腺に残りやすくなります。
これが、緑色を帯びた牡蠣が見られる主な理由です。
また、フランス・マレンヌ=オレロン地方などで見られる「グリーンオイスター」は、珪藻 Haslea ostrearia が産生するマレニン(marennine)という天然色素が鰓(えら)部分に沈着することで緑色に見えるものであり、消化腺の色とは異なる現象です。
参考サイト
商品Q&A | よどがわ生協ホームページ | 生協の安心・安全な商品,お得情報が満載
食べても大丈夫?安全性について
結論から言えば、この緑色は自然な現象であり、色そのものが危険というわけではありません。
緑色の部分は牡蠣の生理的な器官であり、消化腺にはタンパク質やミネラルなどの栄養素も豊富に含まれています。
ただし、注意すべき点もあります。
牡蠣の消化腺は栄養が集中する一方で、環境中の微生物やウイルス(特にノロウイルス)、さらに重金属(カドミウムなど)が蓄積しやすい部位でもあります。
そのため、生食で食べる場合は信頼できる生食用牡蠣を選び、適切に浄化処理されたものを選ぶことが重要です。
もし少しでも鮮度や衛生面に不安がある場合は、中心温度85〜90℃で90秒以上の加熱を行うことで、食中毒のリスクを大きく減らすことができます。
参考サイト
緑色の違いと環境要因
牡蠣の色味は、その個体が育った海域・季節・餌となるプランクトンの種類によって変わります。
特定の海域では、緑がかった牡蠣がむしろ一般的であり、逆に別の地域では見られにくいこともあります。
また、養殖や蓄養(特に「クレール」と呼ばれる浅い養殖池)では、環境中の藻類が変化し、牡蠣の色にも影響を及ぼすことが知られています。
つまり、緑色は環境と生態の自然な反映であり、品質の異常を示すものではありません。
注意すべき異常な状態
とはいえ、すべての緑色が安全というわけではありません。
以下のような状態が見られる場合は、鮮度や品質が落ちている可能性があります。
- 緑色が異常に鮮やかまたは黒っぽく変色している
- 強い腐敗臭(アンモニア臭・硫黄臭)がする
- 身がドロッとしている、または乾燥・萎縮している
- 生貝で殻を叩いても閉じない(死んでいる)
これらの特徴がある場合は、色に関わらず食用を避けるのが安全です。
まとめ
- 牡蠣の緑色部分は、消化腺に蓄積したプランクトン由来の色素による自然なもの。
- 緑色だからといって危険ではなく、通常は食べても問題ありません。
- ただし、消化腺は栄養が集中する一方で、病原体や重金属が蓄積しやすい部位でもあるため、
生食の際は衛生的な管理を受けた牡蠣を選ぶことが大切です。 - 鮮度の見極めには、におい・見た目・産地情報を総合的にチェックしましょう。
緑の牡蠣は、海の生態と環境が生み出す自然の表情です。
正しい知識を持ち、安全に美味しく味わうことで、牡蠣の魅力をより深く楽しむことができます。
以上、牡蠣の緑の部分についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。